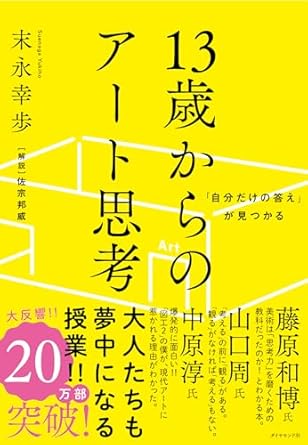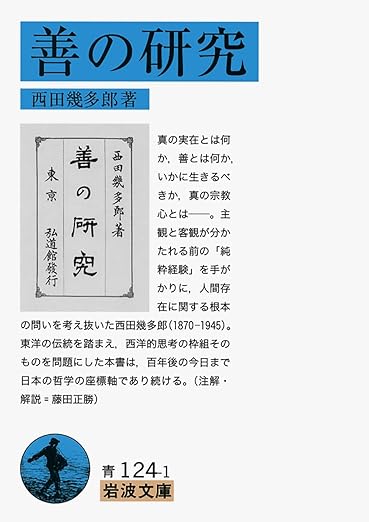EQ COLLEGEコラム⑥
芸術×感情

あなたは、美術館を訪れ展示されている絵画と向き合った時、「絵そのものを見る時間」と
「絵の解説文を見る時間」の、どちらの方が長いだろうか?

これは、数年前に話題になった「13歳からのアート思考」という本の冒頭に登場する読者への問いである。
同書ではこの問いに続いて「おそらく、『ほとんど解説文に目を向けていた』という人がかなり多いはずである」と述べられている。
私は、比較的頻繁に美術館に通っているが、それでもついつい解説文から読んでしまいそうな自分に気づかされる。それは右脳で「感じる」ことよりも左脳で「情報を得たい」「アタマで考えたい」誘惑の方が無意識のうちに勝っているからだろう。
なぜそうなってしまったのか?さまざまな理由が考えられる。仕事では、あらゆる場面で「説明」が求められる。経営者になれば株主に対する説明責任(アカウンタビリティ)を負うことになる。そしてデジタル時代の到来によって「データサイエンス」が急速に広まり、今やMLB(メジャーリーグ)をも席巻している。また、日本に目を向ければ、絶対的な立場だった教師から「正解」を得る習い性が身についてしまった・・・・等々。
だが、誰もが何か新しいものに遭遇した時、それを言語化したり「判断」したりする前に何かを「感じている」はずなのだ。
この主観・客観(=見るものと見られるもの)が区別される以前の直接的経験をしている状態のことを哲学では「純粋経験」と言う。例えて言うなら、圧倒的な自然に接した時、言葉が出ないまま呆然として立ち尽くしてしまうような状態だろうか。欧米に発した概念だが、日本では哲学者の西田幾多郎が、その著書「善の研究」の中で、日本文化に基づいて紹介した。
真実とも嘘とも言えない情報が飛び交い、膨大な情報量の中で自分が好む情報だけを選択してしまう「フィルターバブル」のリスクはますます増大していくだろういま、改めて自分の感情に敏感になる必要性は高まっている。絵画を始めとする芸術には、それを取り戻す媒介としての機能がある。
さて。「13歳のアート思考」では、冒頭の問いのくだりの後、4歳の男の子がモネの「睡蓮」を見た時の反応が紹介されている。彼はこう言った。
「かえるがいる」
もちろん、絵にはかえるは描かれてはいない。しかし、その男の子には確かに「見えた」。誰かが期待する正解ではなく、「自分だけの感じ方」で自分だけの答を導き出したのだ。
私たちは、この男の子のような感覚を取り戻すことができるのだろうか?
再び美術館を訪れる機会があったら、解説文を読みたい気持ちをグッとこらえて、絵を見た時に湧き上がる感情に向き合ってみてはいかがだろうか?