EQ COLLEGEコラム17
選挙×感情
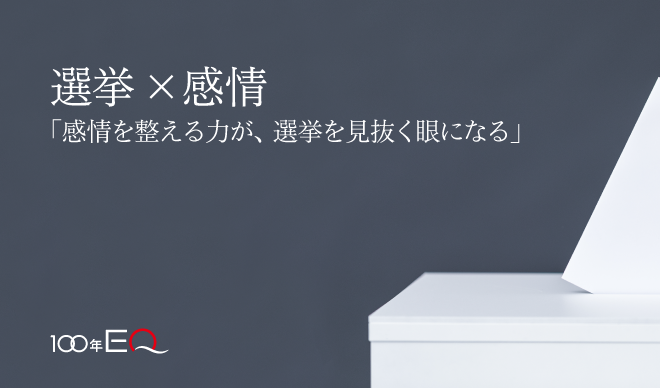
今週末は参議院選挙が行われる。我が家にも、連日選挙カーのスピーカー越しの声が、かまびすしく聞こえてくる。
選挙は、政策という「理」と共に、選挙民の「感情」にどれだけ訴えるかが勝敗のカギを握るが、良かれ悪しかれ政治家の“ハレの場”のためにアドレナリンが高まり、勢い感情的な比重が高まる。加えて、今回の選挙の争点は、「暮らし」や「物価高」になっているだけに、いかに選挙民の切実な願いに気持ちを込めてメッセージを届けるか、も勝敗のカギを握ることだろう。
改めて選挙民である私たちも、候補者が掲げる政策や主張が国や社会全体をより良くする ものなのか?という“理”と、自分の生活をより良くして欲しいという“情”とのバランスをどうとるか、を考えなければならない。
この“理”と“情”のバランスは、メッセージを伝えるメディアにも当てはまる。
我が家は選挙のたびに配布される公報の、ある意味で個性豊かな誌面づくりをながめながら、さてどの候補者に投票しようかを考えるのが楽しみになっている。一方で、この公報はどれほどの人が読んでいるのだろうか・・・・ということも気になる。

若い世代を中心として、SNSや動画の方がより有効な選挙活動になっているからだ。だが、それらのコミュニケーション手段は、加工されたり、不特定多数の人を通じて拡散されたりといった様々なフィルターがあるために、選挙演説や選挙公報よりも、感情を操作しやすいという側面がある。
社会が複雑さを増し、生活の不安も世界的に高まりつつある。「自分さえよければいい」と思う市民の心に自国第一主義あるいは極右化の影が忍び寄るのは、世界のさまざまな場所で起こっていることであり、それは日本も例外ではない。
メッセージを受ける我々にも、「メディアリテラシー」そして「選挙リテラシー」が、ますます求められそうだ。そして、自分の感情を適切にコントロールする能力が、選挙の時にこそ求められる。
夏目漱石の「草枕」の、有名な冒頭文が思い出される。
智に働けば角が立つ。
情に棹(さお)させば流される。
