EQ COLLEGEコラム18
AI×感情
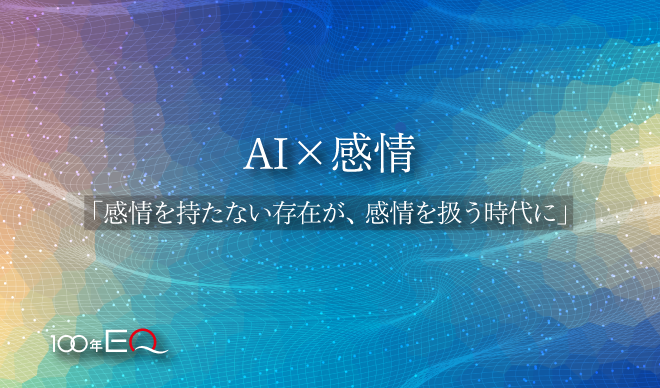
近年、私たちの生活においてAI(人工知能)の存在感はますます大きくなっている。検索エンジンやスマートスピーカー、チャットボット、さらには創作活動にまでAIが関わるようになった今、「AIに感情はあるのか?」「AIは人の感情を理解できるのか?」といった問いが注目を集めている。
AIは本質的に“感情を持たない存在”だ。コンピュータは怒りも悲しみも感じない。しかし、そのAIが人の「感情」を分析し、理解し、時に“寄り添う”かのような言葉をかけてくる時代になった。感情認識技術(Emotion AI)やセンチメント分析(テキストデータに含まれる感情や意見を分析する手法)などの分野では、AIが人の表情・声・言葉から感情を読み取り、対応を変えることも可能になっている。
これは便利である一方で、私たちにとって深い問いを投げかける。
「感情を持たない存在に、感情をケアされることに、私たちは何を感じるのか?」
例えば、孤独を感じる高齢者にAIロボットが寄り添い、優しく語りかける。
あるいは、カスタマーサポートで怒っている顧客に対してAIが冷静かつ共感的に応答する。
感情のプロであるべき人間の代わりに、AIが感情的な場面に介入することで、安定した対応が可能になるというメリットがある。
しかし一方で、AIによって「感情」が定量化・制御され、”最適化”されていく社会では、感情そのものの価値が変わってしまうかもしれない。感情とは本来、複雑で、予測不能で、時に非合理なもの。それこそが人間らしさであり、創造性の源でもあるはずだ。
AIと感情が交差するこの時代、私たちに求められているのは、AIの力を借りながらも、自分自身の感情を見失わないことかもしれない。AIはあくまで道具であり、人間の心の深淵に完全に到達することはできない。だからこそ、AIと共に生きる私たちが、感情という“人間の特権”をどう守り、育んでいくかが問われているのではないだろうか。

実は、この文章はChatGPTに「『AI×感情』というコラムを書いてください」というプロンプト(指示)を行って出来上がって来た文章だ。これを読んで、皆さんの中にはどのような感情が湧き上がってきただろうか?
「AIがここまで“感情”を理解できるのか」だろうか。
それとも「まだまだ人間の感情の本質をわかっていないな」だろうか。
