EQ COLLEGEコラム⑩
地域×感情
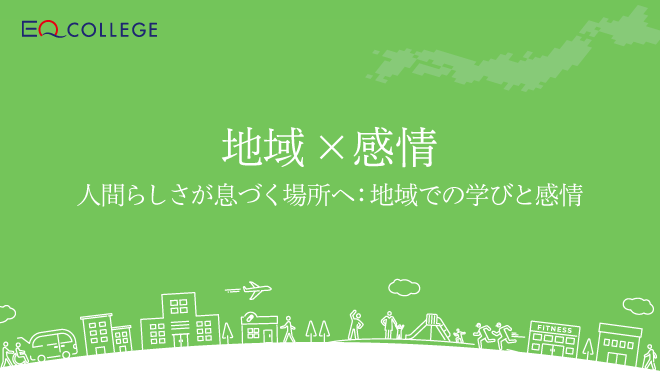
前回は、「所属している組織や環境を離れて、異なる環境で学ぶ」越境学習によって、人は感情がザワつき、自分の中の既存の枠組みを組み直し(リフレーミング)客観的に自分を見つめ直すということをご紹介したが、多くの越境学習プログラムの舞台となっているのが「地域」だ。
企業等の組織に属する社会人がチームを組んで、課題を抱える地方の市町村を活性化させる提案を行う。ではなぜ、地域なのか?
農業、林業などを主産業とする地域には、人口減少をはじめとする日本が抱える問題が凝縮されており、一企業、一組織では出会うことのない課題の本質を考える機会となる。また、普段の仕事では接することのない人たちとの交流を通じて「自分・自社の当たり前」が当たり前ではないことに気付く。加えてSDGsに代表されるように、すべての企業が環境課題への対応を避けては通れなくなっており、それは地方自治体との連携抜きには実現できない。企業にとって、越境学習プログラムは自治体とのパイプづくりの機会でもあるのだ。
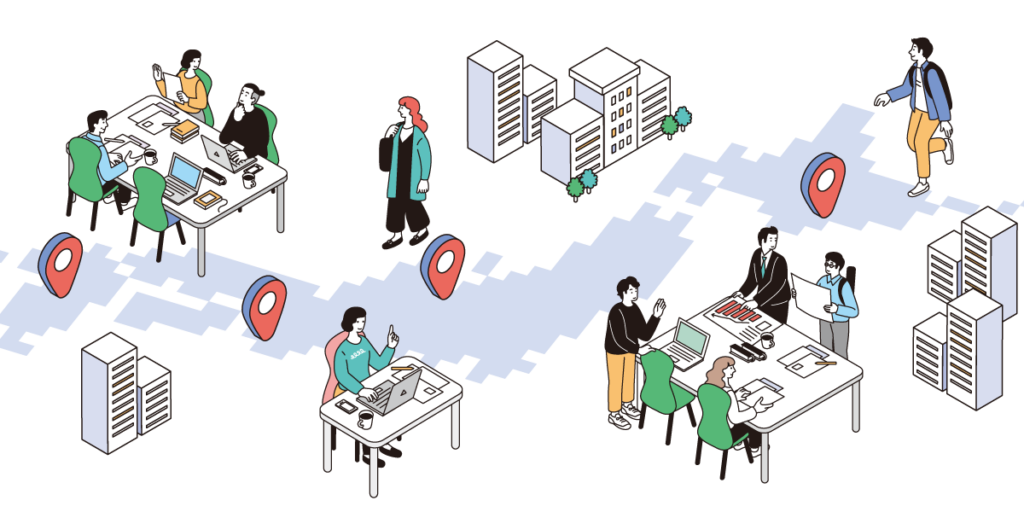
だが、こうしたプログラムを通じた学びの本質は、現地を訪れフィールドワーク等を体験した時、それまで資料やデータを通じて考えたことが机上の空論に過ぎなかったことを知らされることだ。
地域には、人と人の関係性が希薄になった都会では考えられないほど濃密な感情がうず巻いている。綺麗ごとでは済まされない軋轢(あつれき)もある。隣人が困っていると放ってはおけず、お節介を焼く。かつては、都会の下町にも、そうした濃密な関係性があった。
新型コロナ感染拡大を契機に、都会から地方への移住が急増したが、多くの地域では地域住民と移住者との間の衝突が発生している。そのほとんどは価値観が異なる者同士の「感情のぶつかり合い」だろう。それを正当化するわけではないが、生々しい感情のぶつかり合いを経験することで、人は人であることを自己認識するのではないだろうか。
国連の調査によると、世界の都市圏の人口割合は年々増加傾向にあり、都市人口は2015年の約40億人から2030年に50億人を超え、2040年には60億人まで増加すると推定されている。中でも東京の都市人口は2025年まで世界第1位の予測となっており、埼玉、千葉、神奈川を含む東京圏には日本の総人口の約3割が居住するとされる。
地域の濃密な関係性を苦手として都会に移住した人も多いのも事実だろうが、急速に進む都市への人口集中は、ますます、人と人の関係性を薄めていくだろう。
地域には人本来が持っている感情が流れている。人間性を取り戻すためにも、地域に目を向け地域に学ぶ必要性はますます高まっている。
