EQ COLLEGEコラム11
身体×感情
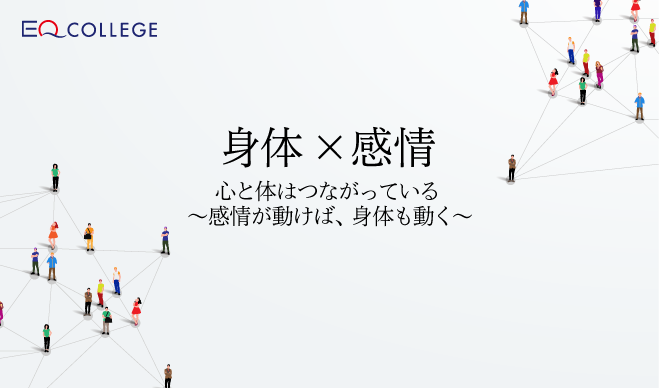
心や感情と身体。どちらがどちらをコントロールするのだろうか。
晴れた日に体調が良いと気分も晴れやかになる。逆に、雨の日に体調がすぐれないと気分も落ち込む。この場合は、体が感情に影響を及ぼす。
逆に、心や感情の状態が体の状態を左右する場合もある。
家の中では歩行がままならない高齢者が、外に出ると歩けるようになることがある。これは「社会化」と言って、人間が社会や集団に適応していく習性だ。人は人との関係 無しには生きていけない。他者から見られている、という自覚が身体を反応させる。
この社会化は、企業や組織にも当てはまる。新社会人が生まれる4月。学生生活から社会人生活に移行する中で、すべての新入社員が新しい環境に適応する「組織社会化」を経験することになる。
だが、この場合、無理に適応しようという心の動きにはリスクも伴う。いわゆる「過剰適応」だ。その結果、五月病になったりバーンアウト(燃え尽き症候群)が起こったりすることになる。

さて。筆者は先だって椎間板ヘルニアを発症した。歩いても、座っても足が痛む。一時よりも落ち着きを見せているが、それでも痛みがある。実は、この「痛み」には2種類あるらしい。本当の痛みと仮想の痛みだ。
後者を「記憶痛」あるいは「痛み過敏」と呼ぶ。痛みを継続的に経験したり、あるいは大きな痛みに見舞われたりすると、それが強烈に脳にインプットされてしまうのだ。そして、大した痛みも無いのに過剰に感じてしまう。または、過去に痛くなった場面と同じ状況になると、実は発生してもいないのに、痛みを感じてしまう。
痛みが生まれる構造は複雑で、専門家でもなかなか解明が難しい。素人が勝手に行動と痛みの因果関係を探ろうとすることは禁物だ。記憶痛(痛み過敏)は、あらゆる事象を左脳的に分析しようとする現代人に特徴的な症状なのかもしれない。
ヘルニアを経験して学んだことは、こと身体については、時には自分の感情に敏感になりすぎないということだ。状況に応じて、感情に敏感になることが必要な時もあれば、鈍感になることが幸せな場合もある。人は、感情に対する敏感力と鈍感力の使い分けが大事なのかもしれない。
