EQ COLLEGEコラム12
マーケティング×感情
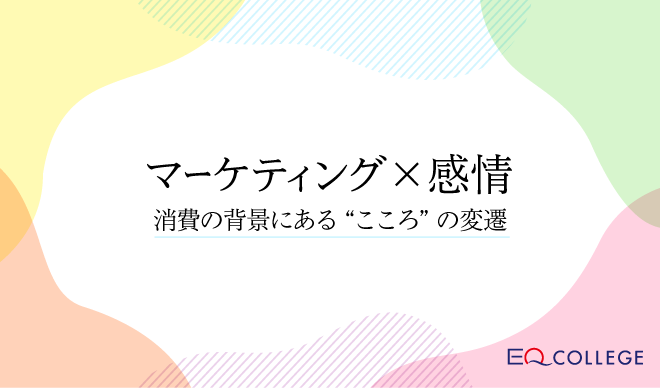
感情とマーケティングは密接に関連している。
ここでは、その歴史を紐解いてみよう。
「マーケティング」という概念が生まれたのは、製品が大量に生産されるようになった18世紀後半のイギリス産業革命まで遡(さかのぼ)らなければならないが、現在のマーケティングの体系をつくったのは、“マーケティング・グル”と呼ばれるアメリカの経営学者 フィリップ・コトラーになる。
彼は、マーケティングの変遷を1.0から5.0まで区切っているが、ここでは3.0までを扱う。 まず「1.0」は「製品中心(product oriented)」のマーケティング。時代区分としては、20世紀に入ってから1960年代頃までが、これにあたる。製品の数が現在よりも極めて限られ、需要が供給を上回っており、そこでは主に新しい製品の機能が価値(Functional value)の源泉だった。要するに、より安価な価格であれば売れていた。
しかし1970年代に入り、技術の発展によって市場に流通する商品が大量になると共に石油ショックという事態が重なり、市場における競争が激化。そして主導権が売り手から買い手へ。「2.0」フェーズへの移行である。ここでは、より良い機能だけでは勝負できず、買い手の感情や情緒に訴えることが価値(Emotional benefit)となっていった。それに伴い「コンシューマーインサイト(Consumer Insight)」という、消費者の潜在的なニーズや行動心理、感情などを洞察する概念や手法が生まれた。
つまり、「いかに人の感情をかき立てるか」がマーケティングの主流になったのだ。
1990年代に入り、インターネットが普及し始め企業も経済活動だけではなく社会的責任が問われると共に、マーケティングも「3.0」へと移行する。ここでは、機能的価値や感情的価値に加えて、精神的価値が重視されるようになる。また「ブランド」が企業の重要な資産価値となっていった。

インターネットの登場によって、消費者の購買行動、つまりモノを購入する時の感情と行動のプロセスも、かつては「AIDMA」と言われた「注意(Attention)~関心(Interest)~欲求(Desire)~記憶(Memory)~行動(Action)」から
「AISAS=注意~関心~検索(Search)~行動(Action)~シェア(Share)」へと変容する。
同時に、マーケティングに感情に深く関わる「経験(Experience)」という新たな概念が登場した。
(つづく)
