EQ COLLEGEコラム13
経験×感情
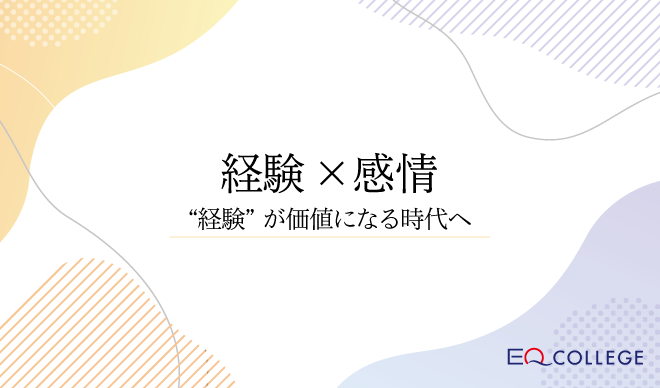
1990年代末、「経験」がタイトルに入る2つの書籍が相次いで出版された。一冊はアメリカの作家、パインとギルモアによる「経験経済」(1998年)。農業~工業~サービスに続く経済の姿を“経験経済”と名付け、企業は顧客のエクスペリエンス(経験)を経済価値としてビジネスを行うことになる、と予言した。
もう1冊は、コロンビア大学の教授 バーンド・H・シュミットによる「経験価値マーケティング」(1999年)。インフォメーション・テクノロジー(IT)の発達、ブランド至上主義の展開、統合型コミュニケーションのエンターテイメントの普及という現象によって、マーケティングがまったく新しいパラダイムに突入した、と提唱した。
シュミットは、フィリップ・コトラーに代表されるマーケティング理論は工業化社会を前提としているため、ITなどによって生まれたコミュニケーション革命や消費者の感情の動きに対応できておらず、包括的な経験を対象としなければいけない、と断じた。筆者は、2000年にコロンビア大学で行われたシュミットのセミナーに参加したが「コトラーなんて時代遅れだぜ!」と本よりも激しいトーンで言っていたことを記憶している(コトラーはその後、マーケティングの理論を時代の変化に対応して「3.0」「4.0」」5.0」へとアップデートしていく)。
しかし、この2冊に先立って「経験」の概念を提唱した本があった。認知科学者 ドナルド・ノーマンによる「誰のためのデザイン」(1990年)である。この本が“UX(User Experience)”という概念を紹介し、やがてHCD(Human Centered Design、人間中心設計)がデザイン領域の主流となり、更に21世紀にデジタル技術が飛躍的に進化するのに伴ってUXは消費者のタッチポイントを指すUI(ユーザーインターフェース)の概念とセットで急速に広まっていく。
また、1990年代に生まれた、顧客が商品やサービスを認知して購入するまでのプロセスを指す「カスタマージャーニー」という概念の導入によって、経験を提供するサービスやコミュニケーションの手法は「面(空間)」と「線(時間)」の両面から進化を遂げていった。
そして2010年代半ば、“経験”の概念は「EX(Employee Experience、従業員体験)」として人事の領域へと伝播する。会社や組織における働き手の体験全般に目を向けるこの考え方は、高齢化や少子化によって労働力が不足する日本においても注目され、近年のエンゲージメントへの重視や人的資本経営の導入が追い風となって広がる気配を見せている。

経済からマーケティングやデザインへ、そして人と組織の領域へと「経験」の概念が広がり、伝播していったのは決して偶然ではない。それは、経済が「モノ」から「ココロ(感情)」へ、企業や組織が「機械」から「生き物」へ、何よりも働き手が「(組織の)部品」から「感情を持つ人間」へと本来あるべき姿に戻っていく必然的なプロセスなのだ。
いま重要なことは、「経験」の価値や意味を伝えるコミュニケーションが、対企業・組織内と対社会とで分断することなく統合・一気通貫されることであり、そのためにもマーケティング、デザインやHR(人事)の多様な専門家が連携・共創することではないだろうか。
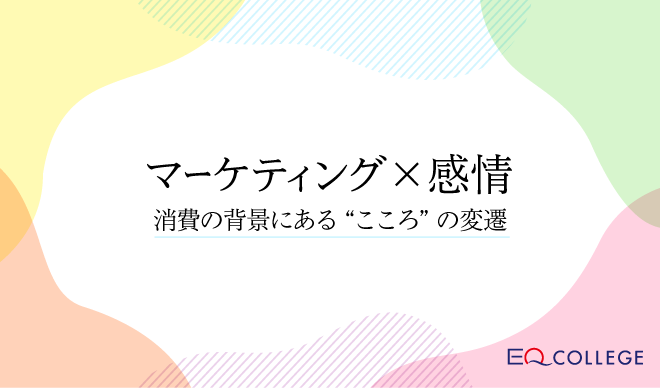
前回コラム
マーケティング×感情はこちら
