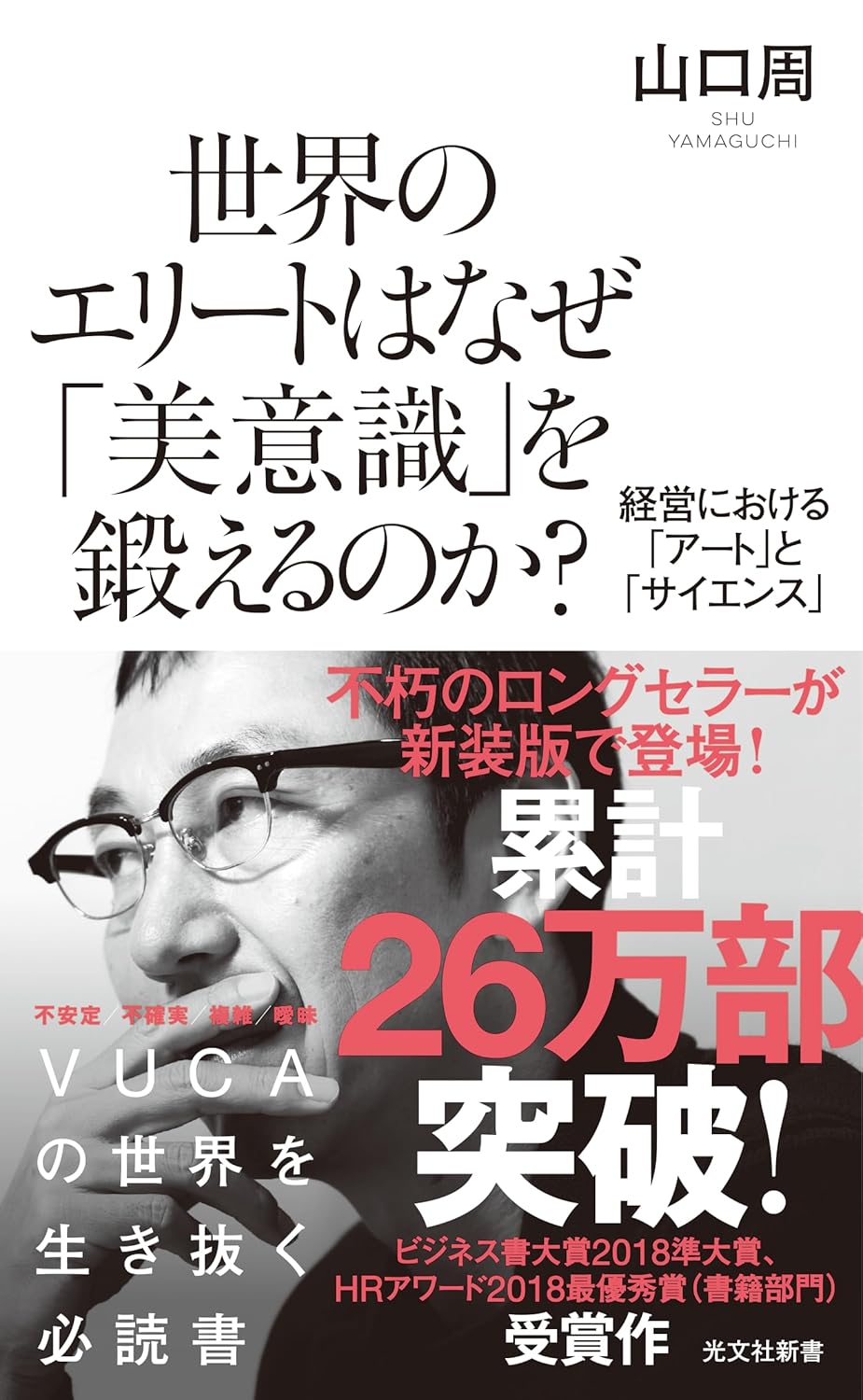EQ COLLEGEコラム21
人事×感情
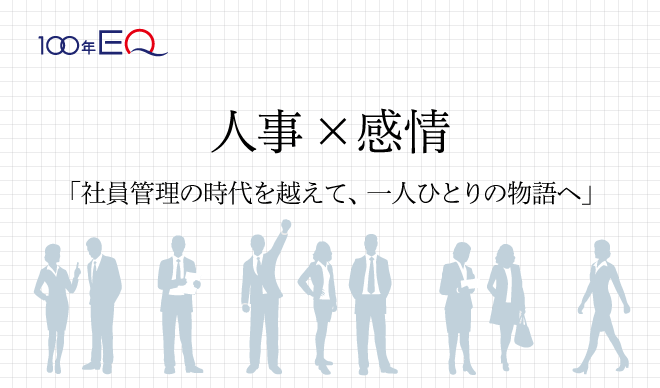
「人事」とは不思議な存在だ。感情を持つ人間を取り扱う役割なのに、なぜか感情の無い存在だと思われる。
その理由を探るためには「人事の起源」までさかのぼる必要がありそうだ。
人事は、産業革命によって工場というものが発生すると共に、増加する労働者を雇用・管理する必要から生まれたとされる。
実は、ここに現在の人事が抱えるジレンマがある。
チャップリンの「モダンタイムス」に見られるような劣悪な環境だった工場労働を見直す転換点となったのが、1924年から32年にかけてウェスタン・エレクトリック社ホーソン工場で行われた通称「ホーソン実験」だった。
何が生産性を向上させるのかの要因を探るために行われたこの実験で、労働者のモチベーション、人間関係や非公式な集団(インフォーマルグループ)といったものが、大きく生産性に影響を及ぼしていることが判明する。
このような実験が行われたにもかかわらず、人事の主な機能は労務管理、人事評価、配置・異動といった「管理」に主眼が置かれて来た。
日本では戦後の高度成長期に、日本独特の雇用システムと言われる「終身雇用」「年功序列」「企業内組合」が確立されていく。
だが、成長を前提としたこのシステムは1990年のバブル崩壊、それに続くグローバル化やデジタル化の波の中で、徐々に形骸化していくことになる。

現在の働き方をめぐるさまざまな「ひずみ」を生んでいる構造的な要因は、人事にかかわる法律や法規が、依然として戦前あるいは戦争直後の工場労働を前提とした管理のままになっていることだ。
2017年の発売以来、ビジネス書として異例のロングセラーとなっている「世界のエリートはなぜ『美意識を鍛えるのか?』」(山口周著)の冒頭には、このような一節がある。
これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない。
システムの変化に法律の整備が追いつかないという現在の状況においては、明文化された法律だけを拠り所にせず、自分なりの「真・善・美」の感覚、つまり「美意識」に照らして判断する態度が必要になります。
人と組織の関係が、会社が一生社員の面倒を見る(これも幻想だったのだが)親子のようなものだった時代から、双方がパートナーに、あるいは個人が会社を選ぶ時代になろうとしている。
人という感情を持った存在を扱う人事には、今こそ「一律・標準的に」社員を管理する思考から、「一人ひとりが異なる感情を持つ」個人の視点に立った本来あるべきマインドセットや行動の転換が求められそうだ。