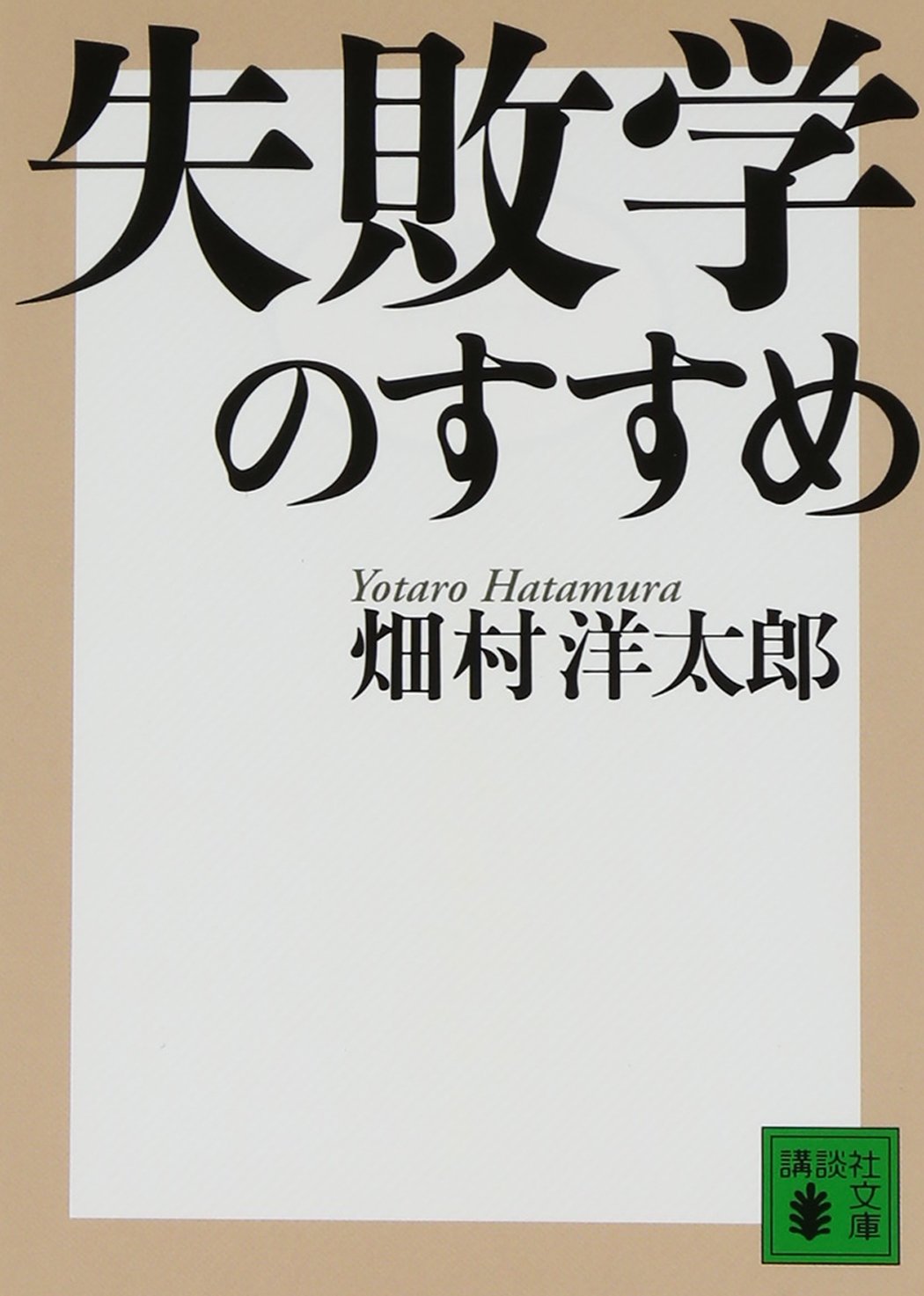EQ COLLEGEコラム22
失敗×感情
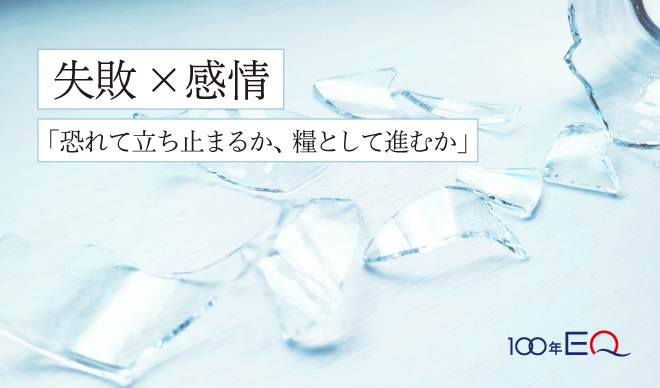
多くの企業の皆さんとお付き合いして感じるのは、日本にはいま「失敗を恐れる病」が蔓延しているのではないか、ということだ。
グローバル化やデジタル化VUCA(変動、不確実、複雑、曖昧)またはTUNA(乱気流、不確実性、新規性、曖昧性)と言われるような「正解が無い」時代が訪れているが、日本の法律やルールといったシステムは生活や働き方の変化に追いついていない。
何よりも、正解を求める「教育」というシステムと正解のない現実社会とのギャップによって閉塞的な空気が広がり、失敗を恐れる気分がやがて「やりたいことが無い」気分につながっていく、という悪循環が生まれている。
厄介なのは、日本には「失敗は成功の母」という良い言葉があったのに、いつの頃からか「失敗は悪」という感情が定着してしまったことだ。そして、多くの組織や企業の中にトラブルを隠蔽(いんぺい)する体質がしみつき、トラブルが明かされると社会全体から糾弾され、それを怖れるあまりさらに隠したくなるというネガティブサイクルが生まれている。

だが、失敗は悪いことなのだろうか?
「失敗学のすすめ」という本がある。
著者は工学博士で東京大学の名誉教授を務められた畑村洋一郎さん。
そこにはこのような言葉がある。
「人間の成長は、失敗なしには語ることはできません。成長の陰には必ず小さな失敗経験があり、これを繰り返しながらひとつひとつの経験を知識として自分のものにしていきます」
そして、このような警告を発している。
「小さな失敗を不用意に避けることは、将来起こりうる大きな失敗の準備をしていることだ」
そもそも、それは失敗なのだろうか?
実は、一見失敗と思われる出来事から生まれた商品や製品は数多くある。
コーンフレークは、パンを焼こうとした際、焼きすぎたパンを細かく砕いたことがきっかけで原型ができたと言われている。
フランスの伝統的なお菓子・タルトタタンは、リンゴタルトを焼こうとして焦がしてしまい、逆さまにして焼いたことで生まれた。
我々が普段使っているポストイットが、3Mの科学者が強力な接着剤を開発しようとして偶然出来上がった「非常に弱い接着剤」から生まれたのは有名な話だ。
「失敗のすすめ」の中では、創造力にすぐれている人には、他の人なら失敗ととらえる出来事の脈絡をつないで新たなものに転換させる「思考のけもの道」のようなものがある、と述べられている。
創造性には「失敗」という概念すら無いのだ!
トラブルを失敗ととらえ、ガッカリしてあきらめてしまうのか。
それを新たな成長への大事なプロセスととらえるのか。
感情と向き合いコントロールできるかどうか、がその分かれ道だと言えそうだ。