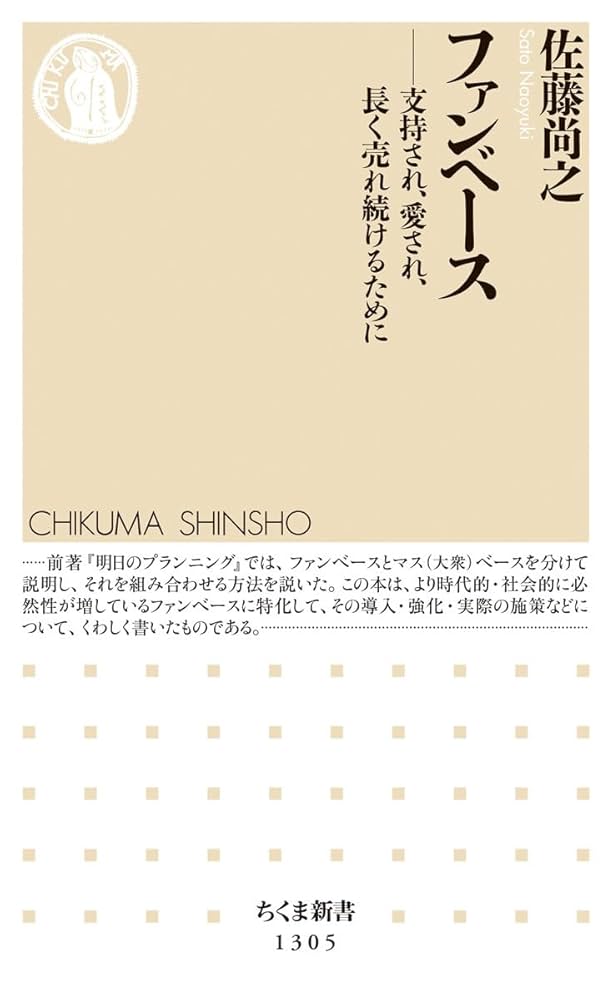EQ COLLEGEコラム23
関係人口×感情

「関係人口」という言葉をご存じだろうか?
日本全国で、人口減少や高齢化によって地域づくりの担い手不足という課題に直面する中、変化を生み出す人材として期待されている、そこに移住した「定住人口」と観光に来た「交流人口」の中間に位置する人たちのことを指す。
関係人口とは|地域への新しい入り口『二地域居住・関係人口』ポータルサイト
総務省の「二地域居住・関係人口」ポータルサイトによれば、地域内にルーツがある人(近居・遠居)、何らかのかかわりがある人(過去の勤務や居住、滞在等)あるいは行き来する人(風の人)などがこれにあたるとされている。近年、このテーマを扱った本が相次いで出版されていることからも関心の高さを表している。
筆者は現在、立命館大学主催、ジャパンラーニング株式会社共催で行われている「チェンジ・メイカー育成プログラム」という取り組みに参画させていただいている。
多様な業種業態で働く社会人が、自社や自組織から越境して特定の地域を活性化させる提案を行う、という内容でこれまで6期に渡って活動して来た。このプログラムを通じて多くの地域との関わりを持った私も「関係人口」ということになるのだろう。
だが、自分が「関係人口」とひと括りにされることへの違和感を拭えないでいた。
さて、このプログラムは今期、石川県・七尾市を対象地域としているが、同市を応援したり愛着を持ってくれたりする人たちを組織化した「七尾ファンクラブ」というコミュニティをつくっている。
私は「関係人口」より、この「ファン」という言葉 の方がすんなりとハラ落ちした。

「ファンベース」というマーケティングの考え方がある。
広告プランナーの佐藤尚之氏が提唱する。熱心なファンを大切にして、ファンの力で売上やブランドの長期的に育てていく、というものだ。
もはや大量生産、大量販売、大量販売ではなくなったいま、「ファン」という存在やその心理・感情着目したこのコンセプトは大きな共感を得ている。
佐藤氏はファンとの関係を深める3つの要素を挙げている。
- 共感の深化:ファンが「このブランドは自分の価値観に合う」と感じる。
- 愛着の深化:ファンが「このブランドから離れたくない」と感じるようになる。
- 信頼の深化:ファンが「このブランドは裏切らない」と信頼するようになる。
多くの人が、何かの“ファン“あるいは“推し”なのではないだろうか。かくいう私はドジャースのファンだが、日々、試合を見続けていく間に上記のような状態に自然になっていった。
地域への共感・愛着・信頼も、「関係人口」という括り方ではなく、
「ファン」という感情に訴えるアプローチで本質的に深まっていくのではないだろうか。